第28号 「研究 Key word」
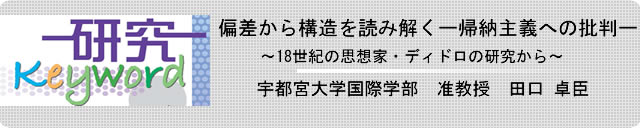
領域横断
大学4年生のとき、友人から18世紀フランスの思想家で『百科全書』の編集者として知られるディドロの『ダランベールの夢』を手渡されました。論点が自然科学から社会科学、人文科学へと領域横断する途方もない作品でした。「石と私の体はつながっているか」。こんな哲学的対話が展開するのですが、その過程でディドロがあぶりだすのは、「いかなる者も対象に対し価値中立的ではありえない」ということでした。
『ダランベールの夢』をきっかけにディドロにのめり込むなかで、私の思考方法もできあがっていきました。いまは、ディドロや18世紀思想における「自然のメカニズムの解明」の問題が、私の研究課題です。
産業技術社会への疑い
ディドロのいくつかの作品は、18世紀科学思想の大変革に関わったテクストとされています。一言で言うと、「合理主義から経験主義に移る革命」、「演繹から帰納に移る革命」のモニュメントとされているのです。
18世紀は、それまで演繹の方法に偏りがちだった思想家たちが、帰納の重要性を再認識した時代でした。実験と帰納を通してつくられた自然観、科学技術を応用していけば学問や社会が進歩し、幸福になっていくという一種の進歩主義史観が芽生えました。ディドロは、この動きの象徴的な存在として引きあいに出されることが多いのですが、きちんと読むと、実は彼は、演繹と帰納の両方を批判しているのです。
では、ディドロは何に注目したのか。さまざまな論点がありますが、私が一番注目しているのは「偏差から構造を読み解く」ということです。例えばコンピュータにバグ(プログラムに含まれる不具合)が発生したとき、通常は「バグは例外的な存在、ノイズに過ぎないので、これを直せばシステム自体はすべてうまくいく」と考えます。それは、ある意味では、帰納主義的な考え方です。
ところが、ディドロの発想はまったく逆で、ノイズこそがシステムを規定しているのではないかと考える。ノイズに見えるものを、例外と見なさないのです。通常であれば、出来事の99・9%が成り立っていればOKと見なしますが、ディドロは、0・1%の側に立つ。0・1%がシステムを壊すのは、どのような場合なのかを考え始めるわけです。破壊的な考え方のようですが、「3・11」の福島第一原発事故後、ディドロの言いたいことがわかったような気がします。

(09年/風間書房)
田口 卓臣(単著)
ディドロの発想からすると、想定外という言い訳は、あってはならない。つまり、期待や法則の外にはみでたものに敢えて注目して、そのシステムが成立する条件を考える。それが、彼の「科学」なのです。偏差から構造を見るというのは、極小の部分への着目を通して「全体」を透視する思考法です。ノイズ、ゆがみ、例外と見えるものに、まさに、全体の縮図を見いだそうとする。
たいていの自然科学者には、この発想が薄いように見えます。その上、彼らは社会的、倫理的にリスクをはらんだものに鈍感になりがちです。その原因は、科学の限界を忘れさせる産業技術社会の仕組みそのものにある。「自然の複雑で変化に富んだメカニズムを前にして人間の認識には限界がある。謙虚になろう」と、ディドロが発していた警告を、私たちは忘れてしまった。このことを証明する論文を書いています。
結晶は極微の弱点から壊れ始める

(2012年5月19日)
私は、「福島乳幼児・妊産婦支援プロジェクト*」で福島原発事故の自主避難母子の支援に関わっていますが、この問題は、世間から見ると例外中の例外とされてしまいます。ひとはまったくこの問題を注視しない。しかし、当事者への聞き取り調査を通して、冷淡に弱者を切り捨てる日本社会の本質が見えてきました。まさに社会の差別的構造がもたらすゆがみであり、放置すれば、たいへんな禍根を残すでしょう。
5月に開かれた本学国際学部主催の公開シンポジウム「3・11原発事故と国際学の未来」にコメンテーターとして参加した私は、雪の研究で知られる物理学者、中谷宇吉郎の『科学の方法』の文章を引用しました。「結晶が壊れるときは、極微の弱点のところから壊れ始める。そして、いったん壊れ始めると、そこがますます弱くなって破壊が進行する。破壊の現象では、極微の弱点が重要な要素として現象を支配する」。「極微の弱点」とは、私の言葉で言えば、「偏差」「ゆがみ」です。
自主避難母子や原発作業員の問題は、例外でも何でもない。日本社会を解体しかねない「弱点」だと私は考えています。
*「福島乳幼児・妊産婦支援プロジェクト」
http://sicpmf.blog55.fc2.com (宇都宮大学多文化公共圏センター)
不在のひとと一緒に考える
ディドロを研究すること、古典を解釈することは、死者とともに考えるということだと思います。これは、ここにいないひとと一緒に考えるという意味で、未来のひとたちとともに考える姿勢とどこかでつながっています。たとえば、未来の世代をおびやかす社会は、仮にいまを生きている地球の60億人が全員同意したとしても、間違っていると言わなくてはならない。ここにいないひとの視点に立つことで、60 億人の同意すら自明ではなくなるのです。
ここにいないひととともに考えない思考は、どこかしら嘘が混ざってくる。死者や未来世代への畏れを持たない思考は、どんな分野の学問であれ、「学問」の名に値しないと私は考えています。

お膳立てされていないものに魅かれて


(写真:右端/ 1999年12月)
学生時代に主演した自主映画が、ぴあフィルムフェスティバルで大賞候補になった。小劇場演劇の俳優・舞台監督も経験し、寺山修司の伝説的な前衛演劇に参加したひとの話に耳をかたむけた。文芸同人誌の執筆・編集。芸術家の指導でギャラリーで展覧会を開催。建築家とともにインドネシアの伝統的な高床式住宅を現地調査した。フランス留学から戻ってからは、既存の経済システムに乗らない、支え合いのネットワークづくりを目指す地域通貨運動にのめり込んだ。
自主映画の監督は、その後商業映画の監督になり、同人誌の仲間には文芸評論家になった者もいる。地域通貨運動では遺伝子組み換え反対の有機農家や、東北の箸職人たちと交流した。学生時代の活動を通して、多様なひとたちと出会えた。「これが私の専門です」と限らず、あちこち無鉄砲に手を出してきたことが、いまの仕事の基礎体力になっている気がする。
同性愛者でないにもかかわらず同性愛をテーマにした映画に主演したのは、いま思えば滑稽だが、やろうと思ったときは、何か嗅覚があったはず。たぶん「これをやりなさい」とお膳立てされたものではないものに魅力を感じたのだと思う。成果があったのかはわからない。恥ずかしい失敗ばかりだった気もするが、そのときそのときで全力投球だった。その経験の濃度というものは、とても大事なことだと思える。


かつて大学には、いろいろな人間が集まってきて、荒唐無稽なことができる環境があった。それが許された最後の時代だったのかもしれない。いま多くの大学キャンパスでは、汚いという理由で立て看板すらない。同じ理由で母校の小劇場や学生寮も撤去された。でも、空間をノイズで埋め尽くすようなものが、大学にはあっていいのではないか。
「渋沢・クローデル賞特別賞受賞」授賞式
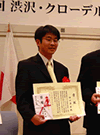
*渋沢・クローデル賞
日仏両国において、相手国の文化に関する
すぐれた研究成果に対して贈られる。(日仏文化会館HP)
国際学部国際文化学科 准教授 田口 卓臣

フランス・モンペリエ市ポール・ヴァレリー大学D.E.A.課程、東京大学人文社会系研究科博士号取得(文学)、日本大学・東京理科大学非常勤講師を経て、現在、国際学部国際文化学科准教授。専門は、18世紀フランスの文学・思想・科学。2010年、『ディドロ 限界の思考』(風間書房)で第27回「渋沢・クローデル賞*」特別賞受賞。